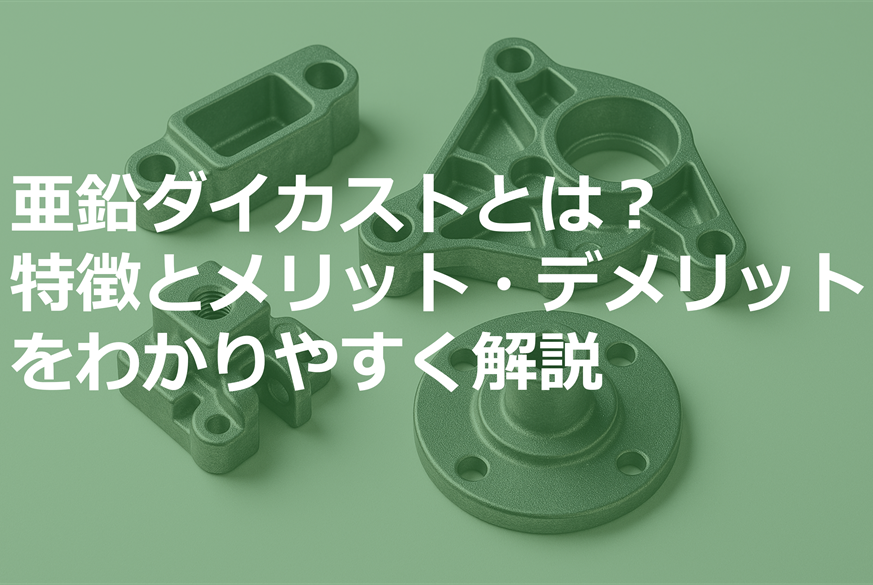亜鉛ダイカストは、溶かした亜鉛合金を高圧で金型に射出し、複雑形状を高精度・短時間で量産できる製法です。自動車・家電・電子機器など幅広い分野で採用され、薄肉化や美観、寸法安定性に強みがあります。本記事では、基礎から特徴、メリット・デメリット、用途やメーカー選定のポイントまで要点を整理して解説します。

亜鉛ダイカストとは
基本の成り立ち
亜鉛合金(ZDC2など)を約400℃前後で溶解し、高圧(10〜100MPa程度)で鋼製の金型へ射出・充填して固化させる鋳造法です。射出・冷却・離型のサイクルが短く、同一形状を繰り返し安定して作れるため、量産に適します。
素材としての亜鉛の特性
亜鉛は比重がやや大きい一方、流動性と鋳造性に優れ、薄肉部まで行き渡りやすい金属です。常温での寸法安定性が高く、メッキや塗装との相性も良好。切削やタップ加工も比較的容易で、二次加工の工数削減に寄与します。
亜鉛ダイカストの特徴
高い寸法精度と薄肉化
金型転写性が高く、微細なリブやボス(カム形状、ギヤ(歯車)、ローレットなど)、細かい文字やパターンも再現可能です。1mm以下の薄肉部品でも形状維持がしやすく、軽量化と材料削減に貢献します。
表面品位と意匠性
鋳肌が滑らかで、ショット・研磨・メッキ・塗装の仕上げが美しく決まりやすいのが特徴であり、見栄えが求められる外観部品にも向いています。
量産性とサイクルタイム
冷却時間が短く、製造サイクルが速いので、大ロット生産でコストメリットが出やすい製法です。多点取りや自動化により、さらなる生産性向上も可能です。
コスト最適化
複雑形状を一体成形できるため、溶接・組立・機械加工の点数削減が見込めます。歩留まりの良さや型寿命の長さも、総合的なコスト低減に寄与します。
メリットのまとめ
亜鉛ダイカストを採用する理由をまとめると以下のようになります。
精密性:微細形状・公差管理がしやすく、ばらつきが小さい
薄肉・軽量:薄肉化と一体化設計で軽量化を実現
外観品質:仕上げ加工との相性が良く、意匠面も高評価
量産性:短サイクルで高い生産能力、リードタイム短縮
トータルコスト:部品点数削減と後工程簡素化で原価最適化
デメリットと対策
比重が大きい
アルミに比べて比重が高く、重量増につながる場合があります。
【対策】リブ配置・肉盗み・トポロジー最適化などで体積を削減し、軽量化設計を行う。
耐熱性の限界
高温環境では機械特性が低下しやすい。
【対策】使用温度域の見直し、放熱設計、樹脂やアルミとのハイブリッド化を検討する。
寸法のクリープ・変形懸念
長期荷重下での寸法変化が課題となる場合があります。
【対策】荷重方向の補強、ボス径やリブ厚の最適化、熱処理・材料グレード選定で抑制する。
腐食・メッキ起因の不具合
表面処理の前処理不備で密着不良が起こり得ます。
【対策】前処理規格の標準化、試作段階で塗装/メッキ条件を確立し、量産で再現性を確保する。
主な用途事例
自動車のドアロック・ヒンジ・ハウジング、家電のヒンジ・ブラケット、産業機器のギアケース、建材の装飾金具、電子機器のシールド部品など。外観と機能を両立したい小型〜中型部品で特に力を発揮します。
設計・製造で押さえるポイント
DFM(量産設計)
抜き勾配・肉厚の均一化・フィレット付与・湯道/押しピン痕の配置を初期段階から考慮します。ガス溜まりやヒケを避け、充填性を高めます。
材質・処理の最適化
用途に応じて合金グレードを選定し、メッキ・塗装・ショットなどの組み合わせで性能と外観を両立させます。
品質保証とトレーサビリティ
寸法検査(CMM)、X線透過検査、リークテスト、外観自動検査の適用範囲を定め、異常流出を防止。工程FMEAでリスクを事前に潰します。

よくある質問(FAQ)
Q. 試作から量産までどれくらいの期間?
A. 金型製作を含めて数週間〜数ヶ月が一般的です。設計凍結が早いほど短縮可能です。
Q. 後加工や表面処理は必要?
A. 寸法や外観要求により選択します。タップ・孔明け・バリ取り、メッキや塗装で機能と意匠を高めます。
Q. コストを下げるコツは?
A. 一体化設計・薄肉化・多点取り・仕上げ簡素化が有効です。早期段階からの共同検討が近道です。
亜鉛ダイカストは、微細形状の再現性、薄肉化、外観品質、量産性に優れ、トータルコスト最適化を実現する製法です。重量や耐熱の制約について設計最適化と材質・処理選定を十分に考慮して、用途に合った設計指針と、実績・検査・一貫体制を備えたメーカーを選べば、性能・外観・コスト削減の全てを実現できます。