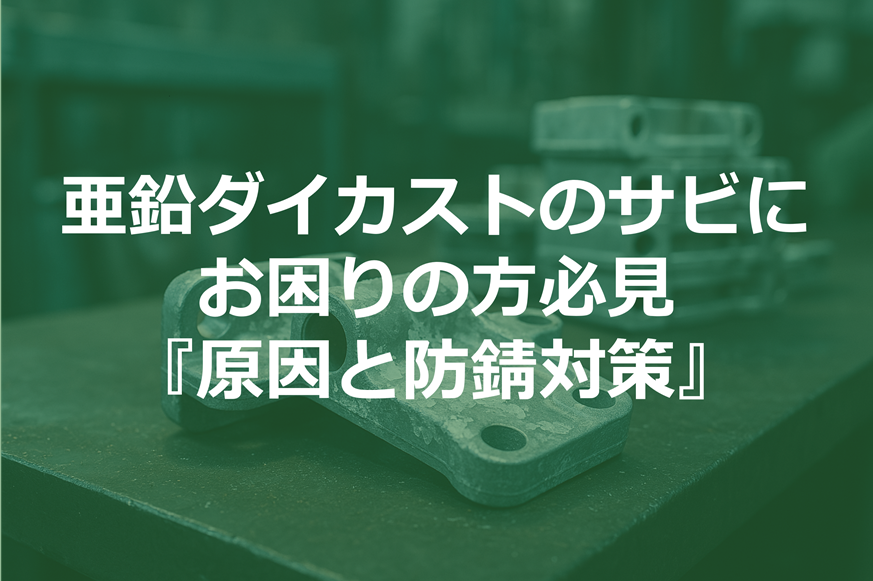亜鉛ダイカストは薄肉・高精度・外観品質に優れますが、環境や表面処理の条件が合わないとサビが発生し、外観劣化や機能不良につながることがあります。この記事では、亜鉛特有の「白錆」を中心に、発生メカニズムと実務で効く防錆対策を、設計・製造・使用の各フェーズに分けてわかりやすく解説します。

亜鉛ダイカストのサビ基礎知識
白錆と赤錆の違い
亜鉛の腐食生成物は白色粉状の「白錆(主に酸化物・水酸化物)」が代表です。母材が鉄鋼の場合に見られる「赤錆」とは別物で、赤錆が目立つときは、メッキや塗装が破れ下地の鉄部品が露出している、もしくは異種材の部位が腐食している可能性があります。亜鉛自体は鉄より卑金属(※)のため、鉄の犠牲防食にも使われますが、条件次第で白錆は短時間で進行します。
※卑金属(ひきんぞく):溶解しやすさ(錆びやすさ)を示すイオン化傾向が大きい金属
発生しやすい環境
高湿度・凝露(朝夕の結露)・塩分(海浜/凍結防止剤)・酸性/アルカリ性ミストが重なると白錆は急増します。保管箱内の密閉湿気や、輸送中の温度差による結露も要注意です。
亜鉛ダイカストの錆の原因をフェーズ別に理解する
亜鉛ダイカストとは?特徴とメリット・デメリットをわかりやすく解説
設計起因の原因
- 水ハケの悪いポケット形状や隙間の滞留水による「隙間腐食」
- 異種金属(銅合金・ステンレス・鋼)との直接接触による電解質存在下で発生しやすい「異種金属接触腐食」
- エッジが鋭い、肉厚が不均一、深いリブ等による膜厚のムラや塗膜割れが原因となる防錆性能の無効化
製造起因の原因
- 前処理(脱脂→洗浄→酸活性化等)が不十分であることによるメッキ/塗装の密着不良やピンホールの発生
- 鋳造欠陥(ピンホール、充填不良、焼き付き跡)の露出による下地の腐食や膨れの発生
- 乾燥不足や水洗残留、ライン内の汚染(油/薬液の混入)による密着低下
使用・保管起因の原因
- 密閉性の高い梱包、高湿・温度差による結露、塩分・薬品飛沫の付着。
- 組立時の指紋・油の拭き残し、現場での傷による下地露出。
- 屋外や海浜での無塗装使用、保守洗浄の不足。
実務で効く亜鉛ダイカストの防錆対策:設計・製造・使用の三段階のアプローチ
設計でできること
- 水切れをよくする勾配やドレン孔の設定、閉じた隙間やポケットを避ける。
- 異種金属を接触させる場合は、絶縁ワッシャや樹脂スペーサ、シール材で電気的に分離する。
- エッジR付与、肉厚の均一化、めっきや塗装が回りやすい形状に最適化する。
- 使用環境(湿度・塩分・薬品・温度)を仕様書に明記し、必要耐久(例:塩水噴霧○時間)を設計要件化する。
材料・表面処理の選定
- 化成皮膜(リン酸塩被膜/クロメート処理):無色~有色タイプ。亜鉛の初期腐食を抑える基本処理として有効。
- ニッケル/クロムめっき:デザイン性と耐食性を両立。下地の前処理・厚み管理が重要。
- 無電解ニッケル(EN):均一膜厚で複雑形状に有利。耐食性が必要な用途に適合。
- 亜鉛めっき+トップコート:クロメート後にシールや有機トップで追加防錆。ボルト類や機構部に有効。
- 塗装(カチオン電着/粉体/溶剤):バリア性と意匠性を強化。下地処理と膜厚管理で耐久性が安定。
用途・コスト・外観要求を踏まえて、複合プロセス(例:化成皮膜+電着、EN+トップコート)を検討しましょう。
前処理と密着性の徹底
- 脱脂(アルカリ/溶剤)→水洗→酸活性化→水洗→乾燥を標準化し、液濃度・温度・時間を記録管理。
- JIS等に準拠したクロスカットやテープ試験で密着性をロット単位で確認。
- 鋳肌のショット/ブラストやバレル条件を最適化し、過度な荒れや残渣を回避。
ライン管理と欠陥低減
- 鋳造条件(溶湯温度、金型温度、射出条件)を安定化し、ポロシティや巻き込みを低減。
- 水洗水の更新、純水リンスの導入、乾燥炉の温度・時間の最適化で水分残りを防止。
- 塗装は膜厚ターゲットと硬化条件を設定し、エッジ部の薄膜やピンホールを監視します。
評価・検証(腐食試験の活用)
- 塩水噴霧試験(中性):比較・監視に有効。白錆発生時間や赤錆到達時間を指標化。
- 湿潤・乾燥サイクル試験:結露環境を模擬。屋内外の実態に近い傾向を確認。
- 化学薬品スポット試験:洗剤や薬品飛沫への耐性確認。
評価結果は図面や工程標準に反映し、必要に応じて処理の積層や膜厚の見直しを行います。
現場で役立つトラブルシューティング
白い粉状の腐食が短期間で発生
梱包内の湿気・結露、前処理不足、化成皮膜未実施の可能性があります。乾燥剤の追加、通気性のある包装、化成+トップコートの追加を検討してください。
点状の膨れや皮膜の剥がれが散発
下地の油残りやポロシティ露頭が疑われます。脱脂強化、酸活性化の適正化、鋳造条件の見直し、シール材や下地めっきの再検討が有効です。
屋外で赤錆が出る
下地が鉄部材で、メッキ層や塗膜が破断している可能性があります。損傷部の補修、膜厚アップ、電着塗装や粉体塗装への切替え、異種金属接触部の絶縁を実施してください。
海浜・寒冷地での腐食が早い
塩分・凍結防止剤の影響です。耐食グレード処理(厚膜タイプに相当する機能の代替、電着塗装+トップコート)や定期洗浄、保護ワックスの運用を取り入れてください。
亜鉛ダイカストの使用・保管での実践ポイント
梱包・輸送
乾燥剤と防錆紙を併用し、密封し過ぎず通気も確保します。温度差の大きい輸送では結露養生するようにします。
現場取扱い・メンテ
• 手の油分は早期腐食の起点になります。手袋着用・拭き上げの標準化を。
• 屋外・海浜では定期洗浄と塩分除去をルーチン化し、傷はタッチアップで早期補修します。

亜鉛ダイカストのサビ対策は、「設計段階で水と異材による電位差を避ける」「表面処理工程で前処理と密着性を徹底」「使用環境・保管状況で結露と塩分をコントロール」の三段階で考えるのが近道です。白錆は条件がそろうと短時間で進行しますが、製品形状の最適化と適切な表面処理方法、そして評価試験によるフィードバックで大幅に抑制できます。
製品の使用環境と要求寿命を数値で定義し、生産工程の標準化とチェックリストに落とし込むことで、外観と機能、コストのバランスを高いレベルで維持できます。